
俺にすがる姿、興奮する
溺あま婚約者の花嫁調教
著者:皆原彼方
イラスト:つきのおまめ
発売日:2月28日
定価:580円+税
尊敬する上司・海棠怜司が突如婚約者となったOLの一宮純佳。
高嶺の花である彼と釣り合わないことに戸惑うが、そのことが逆に彼に火を付けてしまって――。
「心も身体も、俺だけの花嫁になれるように。君を『調教』しよう」
普段は優しい怜司だが、ベッドの上では独占欲強めで、情熱的。
甘やかすことが大好きな彼の執拗な愛撫に蕩かされた純佳は次第に……!?
溺愛と欲望が交わる淫らな花嫁調教が始まる!
【人物紹介】
一宮純佳(いちみやすみか)
大企業を経営する一宮グループの令嬢だが、普段は平凡なOL。
自分の上司である怜司と急に結婚することになり、動揺を抑えられない。
さらには「調教しよう」とまで言われてしまって……!?
海棠怜司(かいどうれいじ)
純佳の上司で、突然の婚約者。
端正な顔立ちから社内では高嶺の花と評される。
そんな自分との結婚に尻込みをする純佳のために『調教』しようと考え――!?
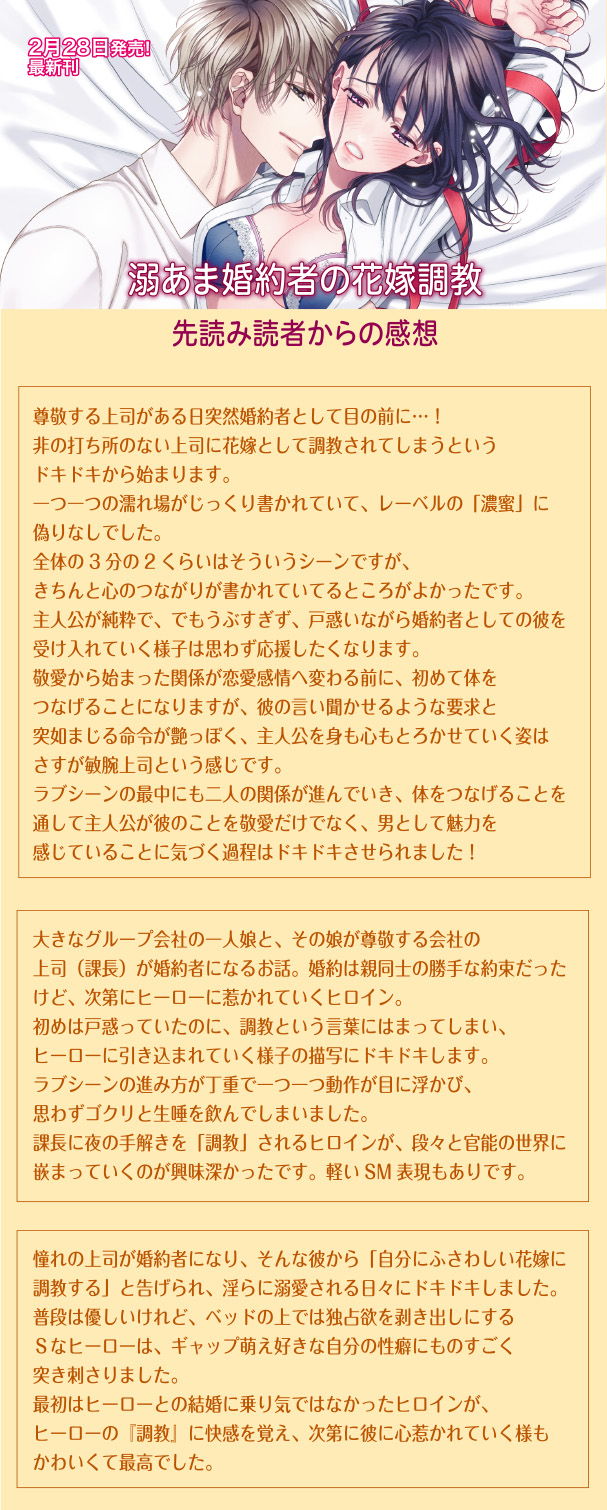
感想の続きは、こちらから! ぞくぞく更新中です。
●電子書籍 購入サイト
| Amazon | BOOKWALKER | honto |
| DMM | 楽天ブックス | 紀伊國屋書店 |
| ReaderStore | Googleブックス | Book Live |
| コミックシーモア | ブックパス | ebook japan |
| yodobashi.com | COCORO BOOKS |
*取り扱いサイトは、各書店に掲載され次第、更新されます。
【試し読み】
「ああ……入ってるぞ。中も熱くて……溶けて、指に絡みついてくる」
かわいい、と耳の裏側にキスを落とした怜司さんが、奥まで押し込んだ指を小刻みに蠢かす。熱い粘膜に纏わりついた蜜が、指に掻き混ぜられて、くち、くちゅ、と鳴った。最奥の窄まりから入り口まで、とろとろの淫液で満たされていると思い知らされる音。内壁を押し広げられれば、その音は徐々にひどくなる。
奥まで沈んだ指先が、最奥の壁を掠めるように撫でた。長い指だからこそ届くであろうその部分は、触れられるたびに鈍く疼くと、小さな口をひくつかせて準備を整えていく。
「奥までよくほぐれてる。気持ちいいと勝手に緩んで……咥え込む準備をするなんて、厭らしいな、君は」
「ぅ、っあ……や、ゃ……」
「ん……いやか?」
「っん……れ、怜司さんに、言われるの……ッあ、っはずかしい、ので……」
落ち着いた声に、淡々と反応を並べ立てられることほど恥ずかしいものはない、――――そう訴える私に、怜司さんはゆるりと首を傾げた。指を鉤状に曲げ、襞の粒を優しく掻きむしりながら、事も無げに囁いてみせる。
「恥ずかしいの、好きなくせに?」
「え、ぁ……」
「言ったはずだ、『君は素直だ』と。俺が君の反応をあげつらってなじるたびに……ここがよく締まる」
嗜虐的な光を双眸に忍ばせて、締め付けを愉しむように指を激しく揺らす。彼のその言葉と手淫に、彼曰く『素直』な内壁が甘えるようにしがみついた。はくはくと唇を震わせる私に、怜司さんの優しくてひどい呟きが降ってくる。
「ほら……また締まった、」
「っあ、だ、だめです、ほんとに……っ」
直截的に反応を揶揄されるたびに、きゅん、きゅんと断続的に淫裂が痙攣し、中を穿つ指を舐め回す。その動きを味わうことを決めたのか、指は戯れを止めてただそこに在るだけの杭と化した。ぴくりとも動かないそれを、怜司さんの言葉に煽られた私が、勝手に『使って』しまう。
ひくりと締め付け、とろりと緩む。ちゅうちゅうとしゃぶるように吸って、指の形を覚え込む。彼の指を使った自慰めいた行為は、望外の悦楽を私にもたらした。私が何をしているかに気付いた彼が、その堪え性のなさを耳元で優しく肯定してくれるから、なおさら。
「一人で好くなれて、偉いな……腰まで揺らして、気持ちいいか」
「んんっ……、ぁ、はあっ、や、きもちい……」
気持ちいいかと尋ねられると、答えを隠せない。唇まで素直な私を、怜司さんがまた甘やかすように褒めそやす。どこかじっとりと濡れた声音を耳穴へと注ぎ込みながら、たまに耳朶を甘噛みしてくるのが、堪らなかった。
耳に与えられる刺激に酔いながら、私はゆらゆらと腰を揺らめかせ、か細い嬌声を漏らす。淫蕩極まりない様相を晒している自覚はあるのに、どうしても止まらなかった。花芯で上りつめた余韻も抜けきっていない身体では、目の前にぶら下がった快感に飛びつかないでいるのはひどく難しい。
「あっ、ぁ、ああ……っは、ふあ、ぁ……」
「は、……っこのまま、一人でイッてみるか?」
「っン、ぁ……っそ、んな、」
「指をもう一本増やして……あとは、ここにも宛てがってやるから。一人で締めて、一人で腰を振って……果ててみろ」
その呟きと共に、中にもう一本指が沈む。温かい蜜を掻き分け、ふやけた粘膜をさらに広げられる感触に背筋が粟立った。加えて、まだ性感の海から抜け出せていない秘芯にも、親指がそっと宛がわれる。どっぷりと快楽に使った頭でも、このまま腰を揺すればどうなるかはすぐに分かった。
かく、と揺れる腰の動きが徐々に速くなる。揺蕩うような快感をくれる中の刺激とは違って、先ほど絶頂をくれた淫芽での快感は直接的で、溺れるほどに強い。独りよがりな律動を繰り返すたび、私の奥が切なく戦慄いて、じくじくとした焦燥が積もっていって、――――
「ひぅ、ッア、ぁ、んんっ……!」
「……純佳。イくときは、『イく』って言うんだ」
いっそ穏やかにさえ聞こえる、劣情に掠れた命令。子供に言い聞かせるような口調のそれが、心の柔い部分を一突きに貫いた。
「ひぅ、っあ、だめっ……い、っちゃ、ぁ、イく……っ!」
ひときわ強く腰を押し付ける。最奥の泥濘を二本の指に穿たれ、押しつぶされた幼気な芽が哀れに震えて。私は喉元を晒したまま、自分が宣言した通りに果てへと駆け上がった。シーツから浮き上がって卑猥に揺れる腰と、精一杯指を引き絞る蜜路が、私の絶頂を怜司さんに伝える。
じわじわと昂った分だけ、余韻も長い。
暴虐めいた悦楽に感じ入り、ゆったりと果てから下りてくるのを待っていると、ややあって彼が指を引き抜いた。いつも私を導いてくれる美しい指が卑猥な液で濡れ、てらてらと光っている。とろ、と薄く濁ったそれが、太い糸となって垂れていくのが見えて、胃の下がじわりと熱くなった。
「は、ぁ……れいじ、さ……」
「……ッ、本当に俺を煽るのが上手いな、君は」
は、と零れた息は火傷しそうなほどに熱い。ゆっくり上体を起こした怜司さんは、膝立ちの状態でスラックスの前を開いた。ぴり、と包装を破るような音に思わず視線を向ければ、はっきりと充溢した屹立に、薄っぺらい膜が被せられていくのが見えてしまう。
「ッ、……」
しっかりと芯の通ったそれは、支えがなくとも勃ち上がり、太く逞しい姿をこちらに晒している。一番太い箇所に至っては、私の手で握り込めるかどうかも怪しいぐらいだろう。
彼への直接的な刺激は、私の拙いキスで全部だ。それなのに、あんなふうに張り詰めているのだと思うと、快感になぶられたばかりの心臓がまた早鐘を打ち始める。
ずっしりと重そうな切っ先から、長い幹を伝って根本まで膜が下ろされていく。たった今満足したはずの下腹部が性懲りもなく疼いて、ひくついて、いけないと思うのに目が離せなくて。彼が『準備』を整える一部始終を、つい熱っぽく見つめてしまった。
その視線に気付いたのか、ふと怜司さんが伏せていた視線を持ち上げる。ばちりと噛み合った瞳が、悪戯っぽく眇められた。
「えっちな子だな、君は」
「は……」
どろりと甘い、私を駄目にしてしまう声が揶揄を紡ぐ。『海棠課長』の唇から出たとは思えない台詞に、衝撃と羞恥がまとめて脳幹を揺さぶった。
その様子が余程おかしかったのか、怜司さんがくすりと笑って続ける。
「……冗談だ。だが、随分と物欲しそうな顔になってるぞ」
「え、っあ、ごめんなさ……」
「いい。君に求められるのは嬉しいからな。……でも、そうだな」
全身からくったりと力が抜け、仰向けに転がったままの私の腰を掴んで、怜司さんが厭らしく舌を舐めた。伏せられた目と合わさって、その光景はぞっとするほどの艶めきを放つ。
「最後に、――――『これ』を強請ってみてくれないか」
口の端だけを吊り上げ、ぞろりとした笑みを浮かべた彼は、腹筋まで反り返った怒張の根本を支えると、その膨らんだ先端で私の淫裂をじっとりと擦り上げた。つられて浮き上がった腰が、びくんと震える。淫路の奥の奥までを穿ち、押し広げてくれるものを求めていた私にとって、焦らすようなその動きはもはや拷問に等しい。知らず、ごくりと喉が鳴る。
「っ……あ、っそれ、」
「欲しい、って言えたら……ここにあげよう。ほら、純佳……言えるな?」
私をさらに追い詰めながら、彼はひくひくと開閉を繰り返す蜜口を突き、溢れた愛液を花弁の中に塗り広げていく。あんまりな唆しだ。そう思っているのに、――――今夜何度もそうしたように、彼の『おねだり』に負けてしまう私は、きっと馬鹿だった。
葛藤を押し込めて、躊躇を振り捨てて、唇を開く。だって、お腹の奥がこんなにさみしい。
「……ッれ、いじさん、の。ここに、ください……」
――――その瞬間、目の前の彼を『余裕のある大人の男』たらしめていた何かが、ぶちりと引きちぎれる音がした。
「ッひ、ぁ、あああ……っ!」
がつん、と腰骨が激しく打たれる感触と、喉までを突き刺されたような圧迫感に脳味噌が揺れる。一拍遅れで、最奥までを彼の剛直に貫かれていることを知覚して、甘えたがりの蜜壁が柔らかくそれを包み込んだ。
ぐう、と上から押さえ込まれ、逞しい腰に軟弱な骨盤を圧迫される感覚すら気持ちいいのが、恐ろしいような、嬉しいような、複雑な感情が胸に広がっていく。
「は、ァ……はいった、な……」
快感にしかめられた眉が、美しいかんばせを一息で雄のものへと変える。耐えるように引き結ばれた唇が、数秒経ったのち、うっそりとした微笑みを浮かべた。燃えるような熱杭は、じくじくと脈打っているのが分かるぐらい、淫襞にぴたりと密着している。大きさと太さをまざまざと思い知らされて、私は髪を振り乱して身悶えた。
「は、んんっ……!」
「ッぐ、……っ! そんなに、……は、締めるな……」
「や、あっ! っん、だってッ……ぁ、ああっ!」
言うことを聞かず、きつく絞ろうとする内壁に対する仕置きなのか、馴染むのを待たずに軽く腰を揺さぶられる。こつん、と奥の壁を突き上げられる感覚。突然の刺激で全身に甘く苛烈な痺れが走り、押された窄まりが、じゅわ、と蜜を溢れさせた。
そこに屹立を留めた怜司さんは、そのまま宥めるように私の鼻先に唇を落とす。
「はー……っ締め方、ちゃんと教えるから……な?」
「っあ、んん……ッはい、」
「ふ、……いい返事だ。まずは入り口側をゆっくり締めろ……ッは、ァ……そう、上手」
ぽたり、と彼の顎を伝う汗が頬に落ちた。彼に教えられるまま、中を締めては緩めてを繰り返す、――――指で一人遊びをしたときと、同じ動き。あれはこれの予習だったのだと思うと、怜司さんの調教の手順と、仕事を教えるときの手順が重なった。
「ッん……奥に入ったら、ここを意識しよう、な。きゅ、……って締めて、内側に気持ちいいの、引っ張るみたいに……」
「ん……っ」
「きゅー、って、ほら……さっきみたいにやってみろ。きゅー……」
「ぁ……っん、ぅ……」
耳元で笑みを含んだ声音が鳴る。彼にしては柔らかく、幼い語彙だった。きゅー、なんて甘ったるく囁かれてしまうと恥ずかしくて、ぞくぞくして、脳味噌が蕩けていくような感覚を味わった。
彼の囁きに合わせ、素直な奥壁が自然と締まる。そこを我が物顔で占領する屹立の、充血し大きく腫れた笠の形まではっきりと分かるような気がした。まろい輪郭、開き切った段差、硬くなった裏筋のライン。その造形に滾った淫壁がさらにしゃぶりつくと、ただでさえ一杯だった狭い蜜洞がひどく圧迫されてしまう。
次いで、笠から伸びる猛々しい幹の硬さ、そこに張り巡らされた血管の数までもを知ろうとするように、襞が小刻みに波打つ。それはまるで、私の蜜壺が怒張を舐め啜っているかのようだった。
「ぁ、っあ、は……」
「ッあ、ぐ……っ、はァ、なんだ、上手いな」
片眉を上げて笑った怜司さんは「君は相変わらず、物覚えがいい」とからかうように呟く。芯まで茹った頭でも、仕事でも何度か言われたことのある台詞だとすぐに分かった。
台詞を起点にして、目の前の怜司さんと脳裏の海棠課長が混じり合い、一つになって、――――やがて眼前で私を穿つ『男の人』の形へと戻っていく。この人が、私を変えてしまう人。私を征服して、花嫁にしてしまう『婚約者』。心の奥底まで、その思考が落ちていく。
私が、海棠怜司という人を、本当の意味で『婚約者』だと認識した瞬間だった。
「これなら、動いても大丈夫そう、だ……、ッ」
「ン、ゃ、ああっ……!」
認識に浸る暇もないままに、掴み直された腰が勢いよく引き寄せられた。快感によって強張り始めていた脚が抱え上げられる。シーツから僅かに浮く形になった双臀に、ぱつん、と彼の逞しい腰が打ち振るわれ、揺れていた爪先がびくびくと宙を掻いた。
緩やかなのにひどく重い、叩き込むような律動。お腹の奥まで揺らされてしまえば、『気持ちいい』以外のことを上手く考えられなくなってしまう。
「ふ、っア、ああっ、んっ!」
「は、はっ……純佳、っぐ、ッあ、」
うっすらと目を開ければ、近くに怜司さんの顔が見えた。腰骨と下生えがぶつかり合うたびに、ぐっと近付くそれが無性に愛おしく思えて、思わず手を伸ばす。
彼の頭を引き寄せるのは簡単だった。首筋に両腕を回せば、誘われるように下りてきた唇が、私のそれに食いついて、咥内を甘やかすように愛撫していく。唾液を混ぜ合わせ、身体の奥を触れ合わせる行為は、泣きそうなぐらいに気持ちが良くて、唇の隙間から零れる吐息がどんどんと高く上擦っていって、――――
「っは、ぁ……ンッ、も、ッイきま、す……!」
「ハ、……っいいぞ、イッて……、ッ!」
涼やかで、怜悧な目元が熱で滲む。砂糖を限界まで溶かしたような視線が、私の痴態を余すところなく見つめる、――――許容量を超えようとする快感に顎が上がり、目の前の人に屈服を示した瞬間、彼の指先がそっと秘所へと伸びた。
「ッ……~~~!」
雷が全身を貫いたような感覚。最奥の窄まりをがつんと突き上げられると同時、二度も苛められ、はしたなく膨らんでいた淫芽を激しく擦り上げられて、私は今日一番激しい絶頂に叩き落とされた。もう一度塞がれた唇に断末魔まで奪われ、圧し掛かられたせいで快感を上手く逃がすことも出来ず、末端までをきつく痙攣させての絶頂。
暴虐を働いたその人にしがみつき、がくがくと震える様はきっと情けないことだろう。表情だってすっかり快楽に染まってしまって、少しも繕えている気がしなかった。
「ッは……はぁー……、は、……んっ、ぅ」
「……っ、ああ、凄いな……」
感嘆の色を滲ませた溜息が首筋にかかる。ぼんやりとした視界の中で、怜司さんはひどく荒い呼吸をついていた。びく、びくっと堪えるように震える怒張を中で感じて、ああ私だけが果ててしまったのだ、と理解する。
「ん、上手に深くイけた、な……かわいい、」
ざらついた呼吸音の合間に降る、優しい声。一緒に降りてきたキスだって、感触は優しいのに、まだじっとりと濡れていて熱い。我慢しているのだとはっきり分かるそれに、私はまだ力の入らない腕を何とかシーツに付いて、ゆっくりと上体を起こす。
「純佳?」
「っわ、私だけ……その、」
――――思い切り、きもちよくなってしまいました。
ぱっと顔を上げて呟いた私に対し、怜司さんは少し眉をしかめてから、ゆるゆると首を振ってみせる。
「気にしないでいい。最初に『妙なことはしない』なんて言ったくせに、散々なことをしたからな……君に、これ以上無理をさせたくない」
ぐっと押し付けられていた腰が、ゆる、と後退する。それを反射的に太腿で挟んでしまったのは、甘美な絶頂の気怠さの中から感傷めいた想いが生まれたからだった。
この人と一緒に気持ちよくなりたい、一人だけなんて嫌だ、――――さみしい。熱に浮かされた心がそんな泣き言を零して、脚が彼の腰へとしがみ付く。海棠課長と結婚するのは違う気がするだとか、『調教』なんて嘘であってくれだとか、そんなことを考えていた数時間前の私とは、まるで別人のようだ。きっと正気に戻ったら羞恥で悶絶するだろうが、今の私の頭は快楽にたっぷりふやかされてしまって、使い物にならなかった。
「っだめ、ですって……口説くなら、最後までちゃんと……」
「……っ、おい」
厚みのある腰が小さく震える。中で大きさを保ったままの熱杭もどくどくと脈打って、彼の唇から短い呻き声が漏れた。先ほどまでより険しくなった眉の角度や、熱量のこもった視線に、つい太腿を擦り合わせるように動かしてしまう。怜司さんの腰を擦り上げる形になったそれを、彼の大きな手が掴んでみせる。
「いいんだな?」
「ん……っ、はい。一人だけじゃ、さみしいから……」
「……分かった。じゃあ『花嫁』殿のお言葉に甘えるとしよう」
は、と吐き捨てるように笑った怜司さんは、軽口もそこそこに私の腰を抱え直した。
「その代わり、俺の好きに動くが……いいか?」
「お……お任せください」
「……ふ、任せた」
私が微妙にたじろいだのが伝わってしまったのか、怜司さんがくすりと笑う。今日の定時までは、滅多に表情を変えない人だと思っていたのに、こうして触れ合い始めてから、色んな表情を知ったような気がする。それは存外いい気分で、私の頬も自然と緩んでいった。
「せっかくなら、体勢を変えるか。こう……」
怜司さんが私の腰を持ち上げ、うつ伏せにひっくり返す。腕が踏ん張れず、上体をシーツへと押し付ける形になった私の「え?」という呟きは無視されて、そのまま下半身を捧げるような格好を取らされてしまった。とろっと緩んだままの秘所を、彼の眼前に曝け出す格好は流石に恥ずかしく、掲げた双丘がひくんと揺れる。
「腰、上手に掲げられてるな。綺麗に反って……厭らしいポーズだ」
「あの……怜司さん、これは、」
「君は被虐を好む性質だろう。恥ずかしい格好で、俺に屈服させられるのが好き。……そうだな?」
「え、あ……っ」
緩んでいた雰囲気が、再び張り詰めていく。漂い始めた濃密な空気が私の呼吸を浅くして、心臓をどきどきと脈打たせた。体勢のせいで、いつ挿れられるかが分からず、まろい双臀の輪郭を撫でられる感触にさえ期待してしまう。息が詰まる。背後の身体の熱が、肌に突き刺さる。
そして全ての音が消えた、一瞬の空白の後、――――灼熱の塊が、じっとりと粘膜を擦り上げて奥を穿った。



